我が家では”家庭菜園で副業!”を目指して、現在ブドウとナシを栽培しています。
僕は自宅の小さい庭(30坪)で、梨とブドウを栽培することで、利益を出すことができるか、いくら利益がでるのかを、実際に試しながら検証しています。
今回は、この家庭菜園の果樹栽培で使用する肥料について、ご紹介していきます。
オール14があれば大丈夫
結論から言ってしまうと、「オール14」があれば事足りると私は考えています。
オール14とは、下の画像のように、窒素・リン酸・カリの成分が14%ずつ含まれている化成肥料のことを言います。
この「14-14-14」とあるのは、左から窒素ーリンーカリを意味しており、数字はその成分%を示しています。
ですので、たとえば「10-10-10」であれば、それぞれ10%ずつ含まれていますし、「10-5-3」であれば窒素10%ーリン酸5%ーカリ3%という意味になります。
作物の生育に必要な成分には、窒素のほか、カルシウム、カリウム、リンなどといった塩基類が必要ですし、マグネシウムや鉄などの金属成分も必要となります。
本来であれば、その土壌に合った、その作物に適した肥料を投入することがベストですが、土壌の状態は場所によって様々であり、作物ごとにも要求される成分は異なるので、最適解を出すのはかなり難しいです。
もし本気でやるとすれば、畑の土を土壌分析し、pHや塩基類などの化学的性質を調べます。
また、その土が粘土質なのか、砂っぽいのかを見極めます。
さらにいうと、もともとの土壌の性質も場所によって大きく異なります。例えば、山土を盛土したような場所では土は比較的痩せており、丘の上にある比較的平坦な場所は比較的肥沃である傾向にあります。
もちろん、ケースバイケースですので、実際にはその畑を見てみないと、その土の性質というものはわかりません。
国の研究機関である農研機構では、日本全国の土壌を調べ、どのような土壌が分布しているかを調査しています。「日本土壌インベントリー」というサイトで、地図から自分の畑がどのような性質の土壌なのかを調べることができます。(必ずしも自分の畑の場所のデータがあるわけではありませんが、近隣の土壌を調べれば、自身の畑についても推測することができます)。
なかなか、最適な肥料バランスや量を決めるのは難しいですし、コストもかかるので、僕はあまり難しいことは考えず、基本的にはオール14(またはオール10、オール8)を使っています。
肥料の使い方
散布量
使用する肥料はオール14ですが、どれぐらい使うかはまた考えなければなりません。
そこで、国や各都道府県が公表している資料などに基づいて、使用量を決めます。
ちなみに、必要な肥料の量は、基本的には窒素・リン酸・カリの3成分のみが示されているのが一般的で、それに合うように肥料の量も調整するのが最適です。
しかし、オール14という各成分の含量が一律になっている肥料を使うので、細かい調整はできません。
その場合は、基本的に窒素の量だけで調整します。
ブドウの場合、10a(1000m2)あたり年間で必要な肥料成分量は、窒素10kg・リン酸6kg・カリ6kg程度となります。
これを正確に散布しようとすると、オール14に加えて窒素のみの単肥(尿素など)を施用する必要があります。
2種類の肥料を買わないといけないのと、肥料を2回まかないといけないので、僕は手間を省くために窒素の量に合わせてオール14の量を決めています。
つまり、リン酸やカリは必要量よりやや多くなりますが、足りないよりはマシだろうという考え方です。
僕の場合、ブドウはだいたい0.4a(40m2)ほどですので、上記から必要量を求めると、窒素0.4kg・リン酸0.2kg・カリ0.2kgとなります。
オール14の1袋(20kg)あたりの各成分量は、窒素2.8kg・リン酸2.8kg・カリ2.8kgとなります。
窒素投下量が0.4kgになるように、オール14の量を計算すると3kgとなります。
つまり、僕の家でブドウを栽培するために必要な肥料の量は、1年でオール14が3kgということになります。
散布回数
僕の場合、ブドウでは1年間でオール14を3kg撒くとわかりました。
では、いつ撒くのがいいのでしょうか。
化成肥料は、一般的に散布してから効果が消えるまで20〜30日ほどとされています。
そのため、一度に3kgを撒いてしまうと、効果は約30日間しか持続しません。
これらのことを踏まえると、僕の場合、4月、5月、6月と約1ヶ月間隔で肥料を撒くようにしています。オール14であれば1回あたり1kgを3回に分けて散布する、というイメージですね。
ナシも同じような考え方です。
ナシはブドウより散布量が多いのと、生育期間が長いので、3月〜7月の5回程度に分けて撒くようにしています。
肥料のあげすぎには注意
露地で栽培している場合、肥料成分のほとんどは作物に吸収されたり、雨で地下に浸透していくので土壌中に過剰に蓄積することはあまりないのですが、肥料をあげすぎてしまうとその可能性もあります。
過剰な肥料は、作物の過繁茂を助長させてしまい、適切な光合成を阻害したり、病害虫発生の原因にもなってしまいます。
特にブドウでは、枝が異常に伸びてしまい、管理が非常に大変になりますので注意が必要です。
年間の肥料量は上述しましたが、あくまで標準的な基準ですので、生育が旺盛な場合は少し減らしてあげるなど調整が必要となります。
ですので、肥料も何を何キロ使ったかという記録をつけつつ、日々の生育の観察を行い、肥料の量を加減しましょう。
まとめ
今回は化成肥料を使った果樹園の肥料散布について、記事にしてみました。
肥料は畑の土壌や作物、生育状況などの要因によって、使う量を調整しなければなりません。
今回はオール14に注目して書いたものの、ホームセンターに行ってみると化成肥料のほかにも鶏フンや牛フンなどの有機質肥料や、苦土石灰といった土壌改良資材も多数販売されています。
これらの資材については、また改めて記事にしてみたいと思います。

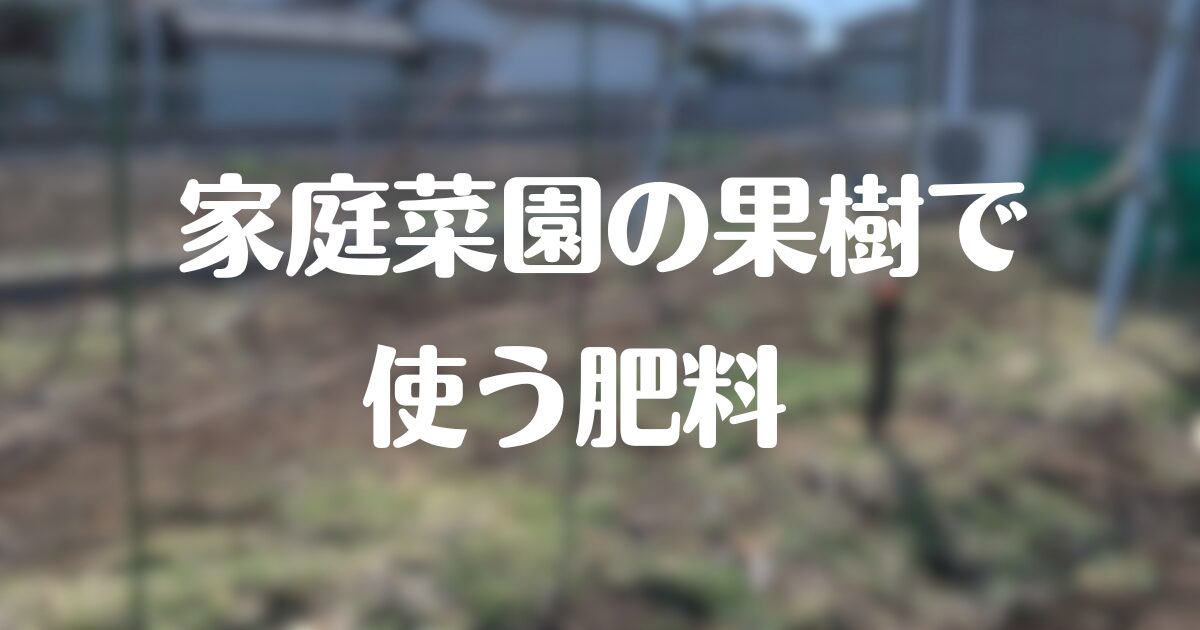
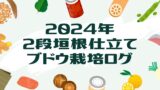
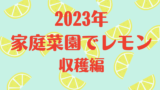


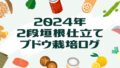

コメント