我が家では”家庭菜園で副業!”を目指して、現在ブドウを栽培しています。
一般的にブドウは平棚で栽培するのですが、我が家の小さい庭(30坪)での栽培であることから、ウチでは垣根仕立てを採用しました。
さらに、欲深い僕は2倍の果実を採るために、主枝を上下2段に配置にさせようと企んでいます。
2022年は初めてブドウ果実を収穫ができ、2023年は樹を大きくしつつ収穫量を上げてきました。
今回は、ブドウの病害虫を抑えるために農薬を使いたいけど、大容量のものは必要ないという方に向けて、ホームセンターなどでも買える小分けされた農薬のご紹介をしていきます。
殺菌剤
サンボルドー
銅を主成分としており、古くから使用されている農薬です。
「〇〇ボルドー」と名前がついている農薬は基本的には銅を主成分としています。
金属の銅は一般的に細菌やカビに殺菌作用を示すと言われており、その特徴を活かした農薬です。
使用するタイミングや回数に制限はないので、いつでも何回でも使えます。
欠点としては、農薬散布後に作物に薬液の跡がついてしまうので、気になる方は果実が付く前や袋掛けをした後に散布するようにしましょう。
オーソサイド水和剤
こちらも古くから、なおかつ世界で幅広く使用されている農薬です。
おもにカビの病害(べと病や晩腐病など)に効果があります。
葉が柔らかいと薬害が出るかもしれないので、使うとしたら葉が固くなってからのほうがおすすめです。
カリグリーン
炭酸水素カリウムを主成分とした農薬で、有機農業でも使用できるのが特徴です。
うどんこ病に効果がある農薬です。
ただし、ブドウではあまりうどんこ病は出ないので、わざわざこの農薬を買う必要はないでしょう。
ベンレート水和剤
多く病害によく効く農薬です。
登録作物が多いので、ブドウ以外も育てている方はとりあえず買っておいても良い商品です。
休眠期と生育期の両方で使えますが、生育期で使う場合、収穫前日数が45日ですのでご注意ください。
殺虫剤
ベニカ水溶剤
ネオニコチノイド系の殺虫剤です。
これ1本でブドウにつく多くの害虫を駆除できるので、1本持っておいても損はないです。
また、ブドウ以外の登録もあるので、かなり重宝する商品ではないでしょうか。
スミチオン乳剤
言わずと知れた殺虫剤、スミチオンです。
こちらもベニカと同様、多くの害虫に効き、多くの作物に登録があります。
今回ご紹介した中では唯一の乳剤です。中身は液体になっていますので、スポイトがあると計量に便利です。
STゼンターリ果粒水和剤
バチルス・チューリンゲンシスという、イモムシのお腹に入ると殺虫効果を示す菌が主成分となっている殺虫剤です。
イモムシにしか効果がないので、見つけたらすぐに撒くか、例年イモムシが発生する時期の前に散布するようにしましょう。
イモムシが大きくなってしまうと効果が低下しますので、小さいうちに使用するのがポイントです。
こちらも有機農業で使用できます。
アーリーセーフ
脂肪酸グリセリドを主成分とした殺虫剤で、有機農業でも使用できます。
他の殺虫剤と異なり、主成分の脂肪酸グリセリドが虫の体を包み込み、呼吸できなくさせることで効果を発揮しますですので、虫にかけないと効果は現れません。
ブドウでは収穫前日までであれば、何回でも使用できます。
また、この剤の特徴としてうどんこ病にも効果があることです。
ブドウで気になる病気
おもに「べと病」と「黒とう病」が発生すると思います。
雨があたる露地条件で栽培する場合、農薬を使用しないとほぼ100%発生する病気です。
農薬以外ではなかなか抑えることができないので、7〜10日の間隔で定期的に散布するのがポイントです。
上記に紹介した3農薬をローテーションで散布することで、効果的に病気の発生を抑えましょう。
ブドウの害虫
ハマキムシやヨトウのような蛾が主要な害虫になると思います。
5月ごろから、これらの虫の発生が多くなるので、早めにゼンターリを散布するようにしましょう。
また、7月ごろになると今度はコガネムシも来るようになります。
こちらは大型の虫なので、農薬はなかなか効かないのですが、必要に応じてベニカを使いましょう。
まとめ
今回は家庭園芸にオススメな小口の農薬についてご紹介しました。
小口の農薬は商品が限られており、選択の幅が狭まってしまうのですが、それでもきちんと使えば効果はあります。
今回ご紹介した商品以外にも、家庭園芸用の農薬はありますので、農園の規模や発生する病害虫に合わせて購入するものも選ぶようにしましょう。


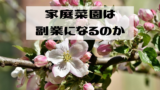
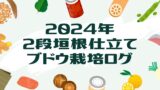
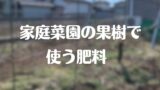
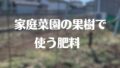

コメント