我が家では「家庭菜園で副業!」を目指し、小さな庭(30坪)でブドウを中心に栽培しています。
一般的にブドウは平棚仕立てで育てますが、スペースの都合で垣根仕立てを採用しました。さらに欲張って、主枝を上下2段に配置し、果実を2倍収穫できないかと試みています。
2022年に初めて果実を収穫し、2023年は樹を大きく育てながら収量を増やしてきました。これまで3回の収穫を経験しましたが、そのたびに新しい課題や反省点が見つかります。
今回はその備忘録として、2025年のブドウ栽培とナシ栽培を振り返り、反省点や学びをまとめておきます。
ブドウ栽培
ジベレリンとフルメット
前回の記事のとおり、今年はフルメットの濃度を減らしました。
ジベレリンは1回目・2回目ともに25ppmです。
- 1回目 フルメット濃度 3ppm → 2.5ppm
- 2回目 フルメット濃度 5ppm → 4ppm
今年は夏が暑く長かったせいか、日当たりのよかった房は8月頃から黄色く色づきました。色だけ見れば十分収穫できそうでしたが、試食してみると酸味が残り、甘味も薄かったため収穫は見送りました。
その後も定期的に試食を続け、実際に収穫できると判断したのは、結局満開から95~100日程度。平年どおりの生育期間でした。
皮の硬さについても、試食のときはやや固いと感じましたが、収穫時にはあまり気になりませんでした。粒の大きさも遜色なく、来年は現状維持か、もう少しフルメットを減らしてもよいかもしれません。
巨峰のつる割れ細菌病のその後
巨峰は昨年、つる割れ細菌病が発生して全く収穫できませんでした。
そこで、昨年秋と今春にボルドー液を散布したところ、今年は発病がありませんでした。
そのため通常どおり房をならせ、無事に収穫まで至りました。ただし病気明け1年目ということもあり、着果量はやや減らして樹への負担を抑えました。
その他の病気や害虫の被害もなく、順調に生育できました。
ナシ栽培
受粉樹の花が少ない
ナシはブドウと異なり、実をならせるには他品種の花粉が必要です。
受粉樹として「あきづき」を1株育てていますが、この品種はなかなか花芽がつきません。
味がよいため一石二鳥と思い、数年前から栽培しているのですが、今年ついた花芽はわずか2個。理想は50~100花芽程度なので、全く足りませんでした。来年以降が心配になり、慌ててホームセンターで「豊水」の苗を購入しました。
今年の受粉は、知人からいただいた花粉のストックを使い、人工受粉でなんとかしました。ただし、そのストックもあと1~2年で尽きそうです。豊水は花芽がつきやすい品種なので、来年以降は多くの花を咲かせてくれることを期待しています。
虫の多発
受粉はなんとかできたものの、着果量が少なくなる不安があったため、今年は本来行わない「1花芽2果実」で栽培しました。しかし、これが裏目に出ました。
お盆明け頃からナシヒメシンクイの被害が急増し、10果実あれば2~3個が被害を受ける状態に。農薬は10日前後の間隔で散布していましたが、効果が十分でなかったのか、発生量が想定以上だったのか分かりません。
700g近くまで大きくなった果実も被害を受け、わずか2個の花芽しかなかったあきづきもやられてしまいました。軽度の被害果は自家消費に回しましたが、腐敗が進んだ果実は廃棄するしかありません。穴に埋める際は、カラスに食べられないよう細かく潰して土をかけていますが、これも手間がかかります。

さらに、カメムシの被害も目立ちました。栽培中に成虫や幼虫をよく見かけてはいたものの、防除は十分だろうと思っていました。しかし結果的には被害が残りました。
2024年は全国的にカメムシが大発生しましたが、今年(2025年)はそれほど多くなかったと聞いています。それにもかかわらず、うちでは発生が多く、防除のタイミングが合わなかったか、周辺環境の影響かもしれません。特によく見かけたのはクサギカメムシで、これは空き家などで越冬します。近所の空き家が発生源になっていた可能性もあります。(ちなみにその空き家はハクビシンの巣にもなっていると思われます…)
カメムシ被害はシンクイに比べて見た目が目立たないため、1果実あたり2~3か所程度ならB級品として販売可能です。しかしあまりにも多いと、外観が悪く売り物にはできません。今年は自家消費に回しました。
最後に
毎年同じように栽培しているつもりでも、必ず何かしらの課題が出てきます。
今年は早めに対策を講じたおかげか、カラスやハクビシンの被害はほとんどありませんでした。
小規模栽培では、1つ1つの被害が全体に与える影響が大きいため、できるだけ病害虫の発生を抑えたいと考えています。
来年はナシについて袋掛けを行うなど、防除を強化して臨みたいと思います。

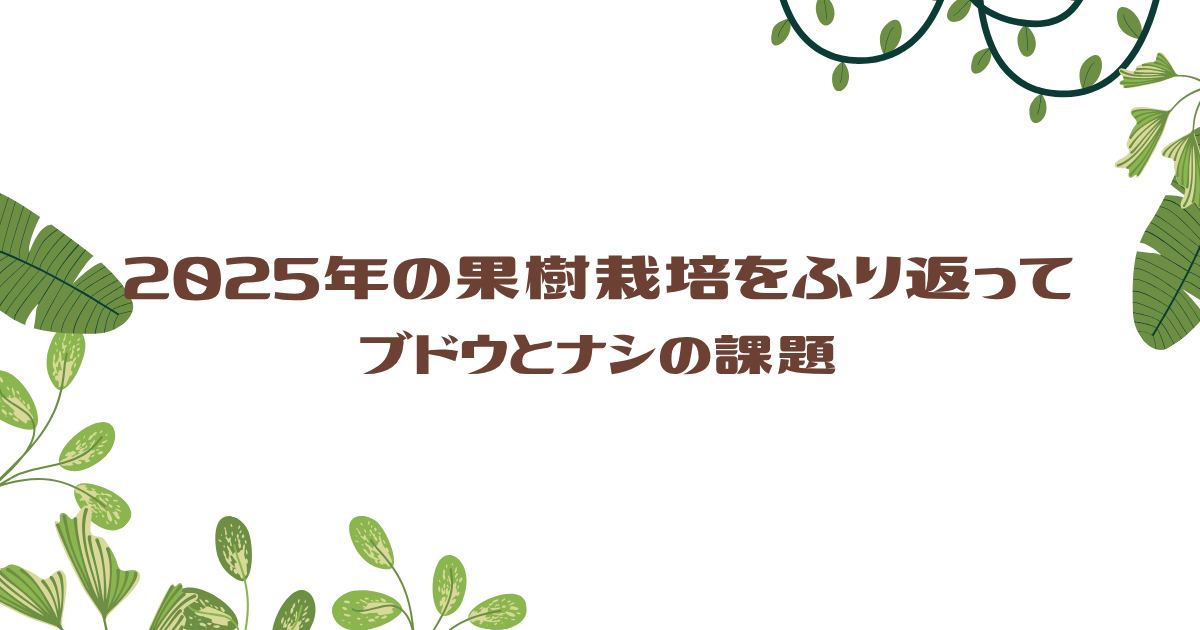

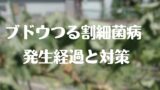
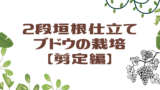



コメント